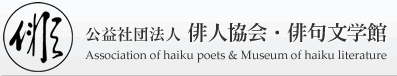俳句の庭/第92回 「川」の履歴書 髙田正子
 |
髙田正子 1959年、岐阜県生まれ。90年「藍生」(黒田杏子主宰)入会。2023年、師の逝去に伴い「青麗」設立。句集に『花実』(第29回俳人協会新人賞)『青麗』(第3回星野立子賞)等。著書に『子どもの一句』『日々季語日和』『黒田杏子の俳句』。編著書に『黒田杏子俳句コレクション』全4刊。俳人協会理事。中日新聞俳壇選者。 |
「川」と聞いてまず思い出すのはふるさと岐阜の長良川である。鮎の上る川として鵜飼は夙に有名だが、私にとっては幼いころに水遊びをした川である。
あをあをと山きらきらと鮎の川 正子
上京してよりは、むしろ木曽川の景に馴染むことになった。帰省の際、名古屋で新幹線から在来線に乗り換え、愛知と岐阜の県境を越えるときに渡る川である。「帰省」の兼題で、
さらさらと青きを渡る帰省かな 正子
と詠んだのは既に四十年以上昔のことだが、鉄橋の振動まで思い出す。
神奈川に住むようになって四半世紀の現在、親しいのは東京との境界を成す多摩川と、東京の東部を流れる隅田川である。隅田川に至っては、その袂で句会をしていたことがあり、
大川のかりがねどきの水のいろ 正子
大川の冬に入りたる波の音
春雷のあと大雨の吾妻橋
などと固有名詞入りで詠んでいるほどだ。リアルな川を見ているのだが、その歴史に敬意を払う心情があるようである。
一方多摩川は日々水道水でもお世話になっているせいか、より一体感がある。親和的過ぎて詠みがたい存在だが、思いがけないときに知らぬ横顔を見て息を呑む。蛇行する多摩川を何度も渡り、遡って行った日、
川渡るころ雪の富士現るる 正子
近く、大きく冠雪の富士を見せてくれた。おそらく、最後まで親しむ川になるのだろう。