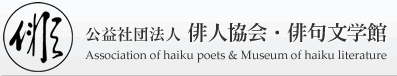俳句の庭/第86回 錦川 福永法弘
 |
福永法弘 昭和三十年、山口県生まれ。 松本澄江、有馬朗人に師事。句集『永』、エッセイ集『俳句らぶ』、『北海道俳句の旅』、共著『角川俳句大歳時記』、『女性俳句の世界』や小説など著書多数。小説『白頭山から来た手紙』で第3回四谷ラウンド文学賞受賞。「天為」選者・同人会長、俳人協会理事。 |
 故郷に大きな川が流れている。錦川という。中国山地の奥深くに源流を発し、瀬戸内海に流れ落ちる山口県東部の急流である。生家はその中流の小集落の中にあった。
故郷に大きな川が流れている。錦川という。中国山地の奥深くに源流を発し、瀬戸内海に流れ落ちる山口県東部の急流である。生家はその中流の小集落の中にあった。
昭和40年前後の小学生の頃、夏休みのほとんどを、その川で過ごした。泳ぎや飛び込み、魚釣りやモリ突き漁、鰻かごの仕掛けなど、近所の上級生に子分のように連れられて、教わるということでもなく自然に身体で覚えた。勉強ができる子よりも、そこら辺の物で臨機応変に遊びをこなす、そんな器用な子が尊敬された。川はひと夏に数回、増水で水嵩が増したり、時には溢れて人家に浸水したりした。そんな時には道端に寄ってくる魚を網で掬ったり、上流から流れ来るボールを拾ったりして遊んだ。大人にとっては気力の萎える洪水被害も、子供には日常とはちょっと違って冒険心がくすぐられる出来事だった。
しかし、平成に入ってから、台風にしても集中豪雨にしても、雨の降り方が異常に激しくなり、土砂崩れは頻繁で、洪水も町を完全に飲み込むほどの高さとなり、川端の家は出水の度に倒壊や流出で減っていき、過疎化と相まって、川沿いに点在していた集落の多くが消失してしまった。公共事業による堤防の強化が何度も行われ、土手は高いコンクリートで覆われて、川辺のネコヤナギもヨシもカヤも消えた。故郷にたまに帰省しても、もう蛍が飛び交う夕空はどこにもなく、真っ黒に日焼けした子供らが水着で走り回る光景は脳裏にしか存在せず、息子の帰りを心待ちにしてくれていたシャイな父親の姿も消えた。
川を見てゐる父の背に帰省かな 法弘