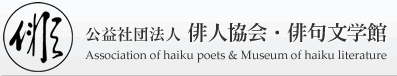今日の一句
- 一月十八日
一月や柱の釘に薬箱 宮田正和 近江や大和が近いせいもあって配置薬を沢山預る。冬になると風邪薬や貼り薬を沢山入れてある。
「宮田正和集」
自註現代俳句シリーズ六(一三)
- 一月十七日
今年より田舎住まひの初詣 寺島ただし 前年の暮に、世田谷より千葉県鎌ケ谷市に転居、「これからは田舎暮らし」の感を深めた。市内の八幡神社にて。
「寺島ただし集」
自註現代俳句シリーズ一二(二三)
- 一月十六日
非凡にも凡にもあらず福寿草 清崎敏郎
対象の景物を一切除去して表面にあるのは「福寿草」だけである。福寿草の本性を包み込んだ情緒と、その名のもつ縁起のよさが融合して、「非凡にも凡にもあらず」と詠まれた叙法の芸の深さに瞠目した。品格の高い福寿草が彷彿としてくる。(井上喬風)
「清崎敏郎集」 脚註名句シリーズ二(二)
- 一月十五日
小豆粥すこし寝坊をしたりけり 草間時彦 中国の人が粥を愛する気持が、このごろ判って来た。なずな粥と違って、小豆粥は明るい。「なづな粥すこし寝坊をしたりけり」では句にはならない。
「草間時彦集」
自註現代俳句シリーズ三(一三)
- 一月十四日
冠着山の風にのりたる吉書揚げ ながさく清江 姨捨伝説の冠着山の麓で、小正月のどんど焼をやっていた。炎は更に風を呼んで、炎屑は冠着山の上空まで昇っていった。
「ながさく清江集」
自註現代俳句シリーズ一一(六〇)
- 一月十三日
初泉五穀作りを安らげぬ 平畑静塔
山梨県での作品。前年暮から正月を河口湖畔のホテルで過ごした。富士に降った雪は溶けては山麓に湧き富士湧水として麓の五穀を稔らせる。「初泉」は泉から汲む初水。新年の泉を言祝いだ句である。(福嶋 保)
「平畑静塔集」 脚註名句シリーズ二(三)
- 一月十二日
門辺掃く成人の日の母として 山尾玉藻 掃除は好きな方である。この日はお向いやお隣の前の道も心をこめて掃いた。
「山尾玉藻集」
自註現代俳句シリーズ一〇(三一)
- 一月十一日
亀甲の罅を吉とぞ鏡餅 山崎祐子 一月十一日の鏡開きに鏡餅を下げて汁粉にした。鏡餅は包丁で切ってはいけないという。罅も入っており、手で砕くのも容易だ。
「山崎祐子集」
自註現代俳句シリーズ一三(三六)
- 一月十日
声乗せて起筆の一字筆始め 能村研三 書道は余り得意ではないが、正月の筆始めの瞬間心に秘めた「声」を乗せて、最初の一文字を書き出した。心の中で練り上げたものを、いよいよ形にする。その最初の、緊張と期待が入り混じった瞬間である。
能村研三 令和七年作
- 一月九日
枕草子をかしをかしと読み始む 西嶋あさ子 清少納言と紫式部は同時代の人。「をかし」について言えば、清少納言の方が人間の幅が広い。言語と人間の結びつきの妙を卒業論文で知り得た。
「西嶋あさ子集」
自註現代俳句シリーズ八(七)
- 一月八日
薺粥妻に仕来りゆるぎなし 水原春郎 仕来りは出来る丈きちんとしようと思っているようだ。美味しい薺粥が運ばれた。
「水原春郎集」
自註現代俳句シリーズ一一(六七)
- 一月七日
人日や岩木はわれの母なる山 桜庭梵子 津軽に住み、何処に居ても岩木山は見える。信仰の山で、津軽人の母なる山である。岩木山を見るとき、ふるさと津軽を感ずる。
「桜庭梵子集」
自註現代俳句シリーズ八(三五)
- 一月六日
寒卵ひところがりに戦争へ 藺草慶子 世界情勢がきな臭くなってきた日々。一月六日、「東山魁夷―わが愛しのコレクション展」を観る。会場を出た時、なぜかこの句となった。
「藺草慶子集」
自註現代俳句シリーズ一三(三七)
- 一月五日小寒
年酒酌む無為をこそ身の幸として 小川斉東語 古稀を迎えるのを機として、会社勤めをすべてやめる決心をした。限りある余生である。健康であるうちに旅行などして、楽しみたいと思った。
「小川斉東語集」
自註現代俳句シリーズ六(八)
- 一月四日
初夢の鶴守となり鶴となり 山口 速 「狩」の新年句会でスコンクだった句。その時は下五が「鶴の中」で当り前すぎた。改作で少し感じが出たかも......。
「山口 速集」
自註現代俳句シリーズ六(一六)
- 一月三日
鶴あゆむ二日の畦のうすみどり 米谷静二 鶴も結構いろいろな角度から詠めるものだと思う。しかし本当は、やはり、まともに鶴自体に挑戦しなければならないのである。
「米谷静二集」
自註現代俳句シリーズ五(二九)
- 一月二日
中の誰が起す風雲初句会 林 翔 「沖」の連衆が一月二日に小宅に集まる慣わしが出来た。置酒高談だけの時もあり、小句会を開く時もある。この日は席題「中」で小句会。
「林 翔集」
自註現代俳句シリーズ三(二六)
- 一月一日
雪卸しして元日もなかりけり 宮下翠舟 妙高山麓の父の生家に遊び、雪国の生活の厳しさを実感した。それでも正月らしい馳走を作り、燃え盛る大炉を囲んでの一家団欒の一刻は楽しい。
「宮下翠舟集」
自註現代俳句シリーズ三(三三)
- 十二月三十一日
狐火の王子二丁目角曲り 髙田正子 大晦日には関東八州のお狐様が王子稲荷に集結するのだとか。このとき角を曲ったのは私だが、狐もそうするのかと思ったら可笑しくなったのだ。
髙田正子 2013年作
- 十二月三十日
大晦日は昔も今もさむき夜ぞ 大野林火 是非「おおつごもり」と訓ませたい。提灯をさげた掛取りも嘗て目にした。しもた屋もこの夜はどこか引緊る。大晦日はただの夜ではない。
「大野林火集」
自註現代俳句シリーズ一(二九)
- 十二月二十九日
一本の冬木をめがけ夜の明くる 望月 周 経験した昼夜逆転の日々。深夜の孤独な作業。自分に真っ先に夜明けが迫ってくるという錯覚。そんなわが身を冬木に置き換えた作。
望月 周 2010年作 句集『白月』
- 十二月二十八日
水仙の一花をさして除夜とせり 向笠和子 商人の大晦日は遅い帰宅である。社宅の小さな床の間の鶴くびの花瓶に水仙のみを挿す。軸は波郷師の「凧の下母の手織の絣欲し」である。
「向笠和子集」
自註現代俳句シリーズ五(六〇)
- 十二月二十七日
年用意父に大壺運ばせて 朝倉和江 正月花は父の好みで大きな花になる。大きな壺は私には持てないから父に運ばせることになる。会社ではいばっている父を使うおかしさ。
「朝倉和江集」
自註現代俳句シリーズ五(二)
- 十二月二十六日
数へ日やふもとは雪の舞ひしのみ 中村雅樹 長野県の南木曽である。山の頂上付近はうっすらと白くなっていた。〈山の雪胡粉をたたきつけしごと〉という虚子の句を、魚目先生が口にされた。
「中村雅樹集」
自註現代俳句シリーズ一三(二〇)
- 十二月二十五日
塵埃車聖樹無惨に運び去る 那須乙郎 クリスマスに子供たちに買い与えた聖樹、終ればすぐ忘れ去られる聖樹、ただ芥となるだけ。
「那須乙郎集」
自註現代俳句シリーズ四(三五)
- 十二月二十四日
まだ若しまだ若し交す年忘 及川 貞 このように言い交し、自分自らも老いを思いたくなく楽しんで一刻を過し、またの一年を期す。
「及川 貞集」
自註現代俳句シリーズ二(七)
- 十二月二十三日
椰子揺れて海ある街や虎落笛 岸本尚毅 南国情緒を狙ってヤシを植えた海辺の小都会。いつしか町は古び、冬は海風に吹きさらされる。そんな町が淋しくも懐かしい。
岸本尚毅
- 十二月二十二日冬至
かかづらふ一事師走のひと日消す 塩崎 緑 うまく事が運ばずとうとう師走の一日が消えてしまった。貴重な一日を失ってしまった嘆きの句でもあり、ドジな自分への自嘲の句でもある。
「塩崎 緑集」
自註現代俳句シリーズ六(一〇)
- 十二月二十一日
村人等酒に舌焼く十二月 有馬朗人 ストーニブルックを辞し、日本へ向う。パリでセミナーの後、何人かでモンサンミシェル、カルナックへ行く。カルナックは古代巨石文化の中心。
「有馬朗人集」
自註現代俳句シリーズ四(四)
- 十二月二十日
国訛りみな威勢よき年の市 小島左京 東新潟火力発電所の関係の仕事をしていた頃、よく新発田や豊栄の市に出掛けた。年の市ともなれば近郊近在の人々でごった返す賑やかさだった。
「小島左京集」
自註現代俳句シリーズ八(五)