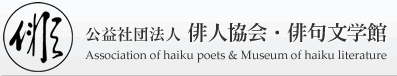今日の一句:2025年07月
- 七月一日
快晴の快風の山開きけり 三田きえ子 「畦」の恒例となっている富士の山開き、快晴の快風のリズムが楽しい。
「三田きえ子集」
自註現代俳句シリーズ七(一四)
- 七月二日
日々待たれゐて癒えざりき半夏生 村越化石 眼を覆われたまま、ベッドに臥して、月余を経た。友人の誰彼が毎日のように見舞ってくれた。
「村越化石集」
自註現代俳句シリーズ二(三八)
- 七月三日
青蔦や若かりし日を手繰り得ず 福永法弘 大学生活を送った学生寮を久々に訪ねた。寮の壁を這う青蔦を引っ張ってみても、懐かしい青春の日々は帰って来ない。
福永法弘
句集『永』より、昨句年2015年
- 七月四日
夏霧に髪濡れて乗る上野かな 蓬田紀枝子 七月四日。みどり女先生にお会いした最後。寝られたままで「杉田久女遺墨を見せてあげて」と家人にいわれた。小さな声だった。
「蓬田紀枝子集」
自註現代俳句シリーズ五(五七)
- 七月五日
身を惜しむ齢は過ぎぬ夾竹桃 本多静江 夾竹桃の赤に対していると、目に見えぬ何ものかに駆りたてられる。耳順も過ぎた身を、今こそ自ら酷使しなければならない。
「本多静江集」
自註現代俳句シリーズ四(四五)
- 七月六日
方角を日にたしかむる破れ傘 小原啄葉 夏の八幡平。チングルマ、トウゲブキなどを眺めながら、沢みちを秋田側に出た。時々方角を間違えては、日輪の位置をたしかめて歩いた。
「小原啄葉集」
自註現代俳句シリーズ四(一六)
- 七月七日小暑
海の門や鰺刺去れば海豚来て 米谷静二 鴨池港は絶好の吟行地、わが家から歩いて三十分で行ける。打ち出しが古風だが、現地に立って下されば幾分かの共感は持たれよう。
「米谷静二集」
自註現代俳句シリーズ五(二九)
- 七月八日
歌仙巻き名残りの裏の心太 伊藤敬子 このごろ月に一巻の割で歌仙を巻いている。連句の知的空間を楽しむ人はもっとふえてもよい。心太も愛好者がふえてきた。健康によいからだ。
「伊藤敬子集」
自註現代俳句シリーズ五(五)
- 七月九日
人として在る寂しさや雲の峰 斎藤 玄 人間として生れ、この世に在るということに、深い寂しさを感じた。孤独感が雲の峰と相摩した日。
「斎藤 玄集」
自註現代俳句シリーズ二(一六)
- 七月十日
一隅に一机一硯夏座敷 上田五千石 十四歳の時、富士郡岩松村に移住。県立富士中学校の文芸誌に〈青嵐渡るや加島五千石〉を発表し、俳号を「五千石」とする。以来、東京に転居するまで、「畦」の基盤を築いた瑞林寺涼月院での歳月を振り返った一国一城の主としての感慨の詠である。(小宮山勇)
「上田五千石集」 脚註名句シリーズ二(一五)
- 七月十一日
ソーダ水まなこいよいよ黒目がち 今瀬一博 ソーダ水の輝き、泡の弾ける音。女の子の会話はとどまることがない。喜々とした聡明なまなこは、いよいよ黒く澄んでいく。
今瀬一博
2022年(令和4年)「対岸」九月号
- 七月十二日
瀧の前生れしばかりの風に触れ 南うみを 生まれたばかりの滝風に心身が洗われる。
「南うみを集」
自註現代俳句シリーズ一二(五)
- 七月十三日
新妻の返事素直や金魚玉 福神規子 仮住まいをしていた時、同じ時期に越してきたお隣さんは新婚さんと見えた。白い新しい家具に囲まれて、幸せ一杯の様子だった。
「福神規子集」
自註現代俳句シリーズ一一(四七)
- 七月十四日
牛舎よりまづしき牧舎夏炉焚く 澤田緑生 立派な牛舎が建っても、開拓の頃から住み馴れた小舎はそのまま残って、素朴な美しさがあった。
「澤田緑生集」
自註現代俳句シリーズ五(一七)
- 七月十五日
白扇の波喪の列の後につく 町 春草 銀座のくのやの主人は、むかしの旦那の風格で、だれにも好かれていた。私も顔を見に店へ寄っては安心して帰る。告別式の日は長い列がつづいた。
「町 春草集」
自註現代俳句シリーズ六(二七)
- 七月十六日
夏芝居柱まつすぐにはあらず 奥坂まや 祖母は明治五年の生まれで、夏の村芝居の楽しさをよく話してくれた。「掘立小屋を作って芝居やるから、柱なんか傾いてるんだよ」。
「奥坂まや集」
自註現代俳句シリーズ一三(三〇)
- 七月十七日
炎天に眼をひつこめて待ちにけり 落合水尾 野球部の監督を七年ほど担当した。県大会に四回出場させることが出来た。ダッグアウトで眼をひっこませながらサインを送り、チャンスを待った。
「落合水尾集」
自註現代俳句シリーズ六(三四)
- 七月十八日
夏風邪のしはぶき妻も覚めてをり 河合未光 床に入ってからも咳。夏風邪は長い。眠ったと思った妻も同調の咳、早く癒えねばと向きを変える。
「河合未光集」
自註現代俳句シリーズ七(三八)
- 七月十九日
子の掌より玉虫の彩とび翔ちぬ 鈴木貞雄 捕まえた玉虫を子に与えた。子供は手の上にのせて見入っていたが、とつぜん、玉虫が飛びたった。その瞬間の鮮やかさ......。
「鈴木貞雄集」
自註現代俳句シリーズ七(二九)
- 七月二十日
落ついて来れば風来る円座かな 高木晴子 七月二十日は千葉の鹿野山神野寺で玉藻の夏行句会と歯塚供養がある。神野寺は虚子の時代から円座や蠅叩、籐椅子などが句材となっている。
「高木晴子集」
自註現代俳句シリーズ二(二三)
- 七月二十一日
氷水いたこの席にとどきけり 皆川盤水 七月二十一日から五日間「恐山」の大祭に死者の霊を呼び寄せる「いたこの口寄せ」が行われる。「いたこ」とは口寄せをする巫子のこと。太く長い数珠を揉む音で霊を呼ぶ、汗を流すいたこの席に現世的な氷水が届いた現実を一句に。写生の力である。(英子)
「皆川盤水集」 脚註名句シリーズ二(一二)
- 七月二十二日大暑
炎天に武人埴輪のがらんどう 河野邦子 埼玉古墳の出土品には埴輪が多い。踊る埴輪、笑う埴輪、女人埴輪、武人埴輪。いずれもがらんどう。
「河野邦子集」
自註現代俳句シリーズ九(三二)
- 七月二十三日
七月の運河見てゐる傘を垂れ 大屋達治 十二人の会深川吟行。富岡八幡宮から江東区芭蕉記念館へ歩いたのだが、途中のこと全く忘れている。アンリ・ルソーの自画像を想うのは何故か。
「大屋達治集」
自註現代俳句シリーズ一一(六五)
- 七月二十四日
雨の日の別れに青きソーダ水 梶山千鶴子 長野県白馬に友人の経営するホテル「トロイメライ」がある。シェフがフランスへ修行に出る日。雨の長野駅近くの喫茶店で。
「梶山千鶴子集」
自註現代俳句シリーズ七(七)
- 七月二十五日
日盛りの言葉捨てたる人ばかり 古賀雪江 一日のうちでももっとも暑い盛りの正午過ぎ、もはや口を開くのも億劫になった人ばかりであった。
「古賀雪江集」
自註現代俳句シリーズ一二(一三)
- 七月二十六日
櫃になほ小袖狩衣土用干し 八染藍子 能の金剛流の家元(京都)の虫干しで、毎年七月に一般公開される。これほど豪華な虫干しは他に類を見ないだろう。
「八染藍子集」
自註現代俳句シリーズ六(三一)
- 七月二十七日
白雲の湧き立つ沖をさし泳ぐ 浅野 正 昔、隅田川の水練場で、日本泳法を習った。夏が来るたびに泳ぎたいと思っていたが、今はもう見るだけで満足している。
「浅野 正集」
自註現代俳句シリーズ六(二一)
- 七月二十八日
睡蓮の閉ぢる刻耳輪重くなる 中村明子 睡蓮は未草。未の刻(午後二時から四時まで)に花を閉じるという。その頃になると、耳輪も重く感じられる。
「中村明子集」
自註現代俳句シリーズ七(二六)
- 七月二十九日
熾見つめ涙ぐむ子もゐてキャンプ 細谷喨々 清里でのがんの子のキャンプ(スマートムンストン)でキャンプファイア。このイベントは様々な思いを子ども達にくれる。
「細谷喨々集」
自註現代俳句シリーズ一三(三一)
- 七月三十日
噴水を立ち去り難し町乾く 森田純一郎 ニューヨーク駐在中に父、峠他「かつらぎ」一行四十人が米国カナダ吟旅に来た時の句。からからに乾き切った町中では噴水さえも貴重な湿りだ。
森田純一郎
平成十年作。句集「マンハッタン」所収
- 七月三十一日
つひの音を地上に曳きて蟬死にき 佐野美智 残りすくない夏を蟬がはげしく鳴いていた。突如一羽がひいっという音を曳いて地に堕ちて死んだ。何年かたって出来た句。
「佐野美智集」
自註現代俳句シリーズ四(二四)