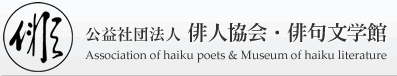今日の一句:2025年05月
- 五月一日
藤を見に天神様の小径抜け 菖蒲あや 亀戸の天神様はわが家から歩いても僅かの距離である。子供の頃から何かにつけ遊びに行ったものである。初天神と藤の頃は人手も多い。
「菖蒲あや集」
自註現代俳句シリーズ二(一九)
- 五月二日
粽解き孝養足るといふことなし 倉田春名 子供の頃は虚弱で随分親に心配をかけた。父は子供達の健康には極めて神経質で、母は一層苦労した。母には是非長生きして貰わねばならない。
「倉田春名集」
自註現代俳句シリーズ六(五三)
- 五月三日
つぎの風待つ矢車の小休止 有吉桜雲 音たてて廻ることこそが矢車の使命。ただ使命感一心に追いまわされてばかりでは過労になる。
「有吉桜雲集」
自註現代俳句シリーズ八(四五)
- 五月四日
父の掌の温みは知らず柏餅 中尾杏子 父は私が十歳の時に亡くなった。外資系の電信会社の技師だった。数冊の日記と一冊の詩集を残している。家の二階で時々、俳句会をしていた。
「中尾杏子集」
自註現代俳句シリーズ一〇(一五)
- 五月五日立夏
金網影踏みて白鶏夏に入る 伊藤京子 日当りのよい農家の庭。鶏舎を出た雄鶏が胸を張り鶏冠を立てて歩いていた。とさかの紅色と真っ白な羽の色が夏にふさわしい。
「伊藤京子集」
自註現代俳句シリーズ一〇(四)
- 五月十日
匂ひなき花咲きつぎて森五月 渡邊千枝子 五月の森ほどかぐわしいものはあるまい。花の香などはいらない。そういえば森に咲く花は白い、無臭の花が多い。
「渡邊千枝子集」
自註現代俳句シリーズ八(三)
鯉幟きそふ緑のありてよし 後藤夜半
五月七日、玉垂会は箕面市牧落の寧楽庵。奈良鹿郎旧居である。鹿郎は昭和三十五年八月十五日、大阪逓信病院にて逝去。享年七十二歳。この日鹿郎忌が行われ、そういった中にこの鯉幟の句が異色である。「きそふ緑」は見事だが、「ありてよし」がやや不本意かも。
「後藤夜半集」 脚註名句シリーズ一(八)
- 五月八日
富士ぬつと旧の端午の甲斐の国 永井由紀子 実家からは見えない富士山。勝沼あたりを吟行しているといきなり現れた。何だか父に逢ったようで嬉しい。
「永井由紀子集」
自註現代俳句シリーズ一二(三六)
- 五月九日
菖蒲湯に浮かばせ対の膝がしら 鷹羽狩行 快い菖蒲湯と遊ぶ者は、自分のほかに膝小僧二人。
「鷹羽狩行集」
自註現代俳句シリーズ・続編七
- 五月六日
緑陰や光るバスから光る母 香西照雄 銀バスから転び落ちるように下車する瞬間、母の髪や顔がピカリと光る。子が薄暗い木陰で待ちわびていたので、バスも母も特にまぶしく見えた。
「香西照雄集」
自註現代俳句シリーズ一(二一)
- 五月十一日
夏場所の近きや深川めし処 佐藤麻績 夏場所は五月場所ともいう。深川飯とはあさり御飯のこと。江戸の下町らしい雰囲気に通い合うものがある。
「佐藤麻績集」
自註現代俳句シリーズ一二(二五)
- 五月十二日
美作へ十里余りや若葉雨 高木良多 「美作へ十里」という標識に、剣客の宮本武蔵と俳人西東三鬼の名を思い出していた。
「高木良多集」
自註現代俳句シリーズ五(四四)
- 五月十三日
葉桜一樹もて覆ふべし女人堂 吉町義子 高野山の女人堂のそばに大きなさくらが一樹ある。花を終ったばかりのその樹を見ていて、早く葉桜となり堂を覆いつくしてほしいと思った。
「吉町義子集」
自註現代俳句シリーズ四(五四)
- 五月十四日
混浴の湯は湖に向き夜の新樹 熊谷佳久子 昔の丸駒温泉は、混浴だった。青邨先生との句会の後、母と一緒に入浴。玻璃戸越しの新樹が素晴らしかった。
「熊谷佳久子集」
自註現代俳句シリーズ一三(二九)
- 五月十五日
御仏に目を覗かるる薄暑かな 大竹多可志 伏し目の仏像が上から、私の目を覗き込み、何か、もの言いたげであった。しっとりとした堂内の薄暑の闇が御仏と私を一体化している。
「大竹多可志集」
自註現代俳句シリーズ一二(四四)
- 五月十六日
麦笛や見様見真似で吹いてみる 日下野仁美 麦笛はすぐには吹けない。吹いている人を真似ながら自然と覚える。私の場合は次兄に習った。
「日下野仁美集」
自註現代俳句シリーズ一三(一七)
- 五月十七日
福耳の祖父とうに亡し麦の秋 戸恒東人 第一句集『福耳』上梓。父も祖父も福耳であった。祖父や父はこの句集にどんな感想をもらしたであろうか。
「戸恒東人集」
自註現代俳句シリーズ一〇(九)
- 五月十八日
五月場所判官贔屓に徹しけり 水原春郎 私は何につけても判官贔屓の性。義経は勿論、野球は弱いチーム、相撲も小兵力士を応援している。
「水原春郎集」
自註現代俳句シリーズ一一(六七)
- 五月十九日
新緑の夜は馳けだすか石の鹿 木内怜子 日比谷公園へ野外石像展をみに行った。前脚を上げた鹿の石像。こんな姿勢で静止し続けるはずは無い。
「木内怜子集」
自註現代俳句シリーズ七(四一)
- 五月二十日
心濡るゝまで牡丹に遊びけり 小林鹿郎 同右。百態をつくす牡丹に、火焔のすさまじさを見ていながら、心はいつか濡れてゆくふしぎさ。
「小林鹿郎集」
自註現代俳句シリーズ六(二二)
- 五月二十一日小満
ばら五月女に彩を著る楽しさ 大橋敦子 ばらは多彩に花圃を彩る。女性の衣服というものも、華美の世にこれまた多彩。
「大橋敦子集」
自註現代俳句シリーズ二(八)
- 五月二十二日
朴の花夢に高さのありとせば 南うみを 高所に毅然としてひらく朴の花が好きだ。
「南うみを集」
自註現代俳句シリーズ一二(五)
- 五月二十三日
霽れてゆく如く新茶の香の流れ 廣瀬ひろし 大和紡績の職場句会の作。句材に新茶が持参してあった。幹事の配慮で早速心配りの湯加減で淹れられたが、雨が霽れてゆくように香が拡がった。
「廣瀬ひろし集」
自註現代俳句シリーズ六(四九)
- 五月二十四日
富士にゐて富士無き茅花流しかな 久保千鶴子 延平いくとさんの御世話で山中湖畔吟行。霧雨の中で郭公と大瑠璃を聴いた。一面の茅花で、茅花流しの季語を初めて使えた。
「久保千鶴子集」
自註現代俳句シリーズ八(一一)
- 五月二十五日
髪刈られゐる鏡中を神輿来る 奈良文夫 行きつけの理髪店。うとうととした眼に神輿をかつぐ少年の自分があった。
「奈良文夫集」
自註現代俳句シリーズ八(二七)
- 五月二十六日
縮緬もちぢみも盛り菖蒲園 伊藤トキノ 花にもいろいろあるが、しょうぶほど日本的な花は無いように思う。
「伊藤トキノ集」
自註現代俳句シリーズ七(二三)
- 五月二十七日
家に母ひとりを置けり祭笛 伊藤通明 村の社は多くがそうであるように森の中にあった。祭の日、笛や太鼓が森にこだましていて、いつか気がつくと母だけが家に取り残されていた。
「伊藤通明集」
自註現代俳句シリーズ四(九)
- 五月二十八日
咲き遅れたる白さあり山法師 照井せせらぎ 啄木祭の帰途すでに終わったはずの山法師の花が、奥の森林にちらほら見えた。咲き遅れた白さもまた格別である。
「照井せせらぎ集」
自註現代俳句シリーズ一〇(三)
- 五月二十九日
雲触れて花ふやしたり山法師 白岩三郎 山の中腹にある山法師が咲いた。低い雨雲の去った後など、また花の数が増えたような気がする。
「白岩三郎集」
自註現代俳句シリーズ六(三九)
- 五月三十日
万緑を来て酌む木曾の七笑 加古宗也 木曾は「木曾五木」に代表される美しい森林を持つ国。そして「七笑」に代表される美酒の生まれる国。俳句仲間と木曾の温泉郷に投宿した。
加古宗也
- 五月三十一日
たちまちに天地さかさま夏燕 角谷昌子 子育てで忙しい燕たちは、南アルプスの嶺々を背景に餌を求めて飛び回る。日々濃くなる緑の中、翼で風を切り、見事な宙返りを見せてくれる。
角谷昌子
「磁石」9月号所収 2024年