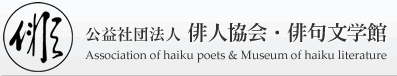今日の一句:2025年03月
- 三月一日
皿沈む水のあかるさ雛の家 井上 雪 天井があかるくなり、何となくまわりが活気づいてくる雛のころが好きだ。食卓の一隅で原稿用紙をひろげ、皿を洗い、また原稿を書く日常。
「井上 雪集」
自註現代俳句シリーズ五(三六)
- 三月二日
初雛や嬰は全身でよろこべる 伊東宏晃 次女の児の初節供の祝に、妻と見立てた人形が、児にとってどんなにか嬉しかったのであろう。
「伊東宏晃集」
自註現代俳句シリーズ九(一〇)
- 三月三日
雨の日のあたためてある雛の間 西山 睦 雛壇に尉と姥の人形が加わったのは三・一一後。津波にあった知人が送ってきた。人形からは常に砂がこぼれる。捨てられずに私の元へやってきた。
西山 睦 句集『春火桶』より
- 三月四日
白酒の瓶に桃花を描きけり 阿波野青畝 女たちの宴に招かれた。はこばれたのは白酒の瓶、なめるだけでよく、深く酔いたくない仲間である。レッテルに桃の花が似あわしいと思えた。
「阿波野青畝集」
自註現代俳句シリーズ一(二七)
- 三月五日啓蟄
啓蟄や使はぬ部屋に日の射して 宮崎すみ 殆どが使わぬ部屋になったようだ。そんな部屋に、時おり日が射す。虫たちの活動もそろそろ、あの賑やかだった昔はどこに行ったのだろう。
「宮崎すみ集」
自註現代俳句シリーズ一二(四)
- 三月六日
欄間越し雛雪洞を閨明り 品川鈴子 真っ暗で眠る習慣だが、二間続きの座敷に雛を出して、こうした間接照明もまんざらでは無い。寝室が何となくなまめかしい。
「品川鈴子集」
自註現代俳句シリーズ五(四二)
- 三月七日
桃花一束酩酊に似て抱へ来る 山田みづえ 毎年三月に味わう気分。大きい壺にワァッと活ける。桃源境には及ばずとも。
「山田みづえ集」
自註現代俳句シリーズ・続編一五
- 三月八日
パンク穴より早春の泡の列 今井 聖 今井 聖
『バーベルに月乗せて』所収 作句年2005年
- 三月九日
万葉の里のかんばせ沈丁花 渡辺雅子 「青山」いづみ句会吟行会。岩崎あつ子さんのお世話で近つ飛鳥の里。太子町へまず昼食に。南魚水先生と上田和子さんと相席で肉南蛮を......。
「渡辺雅子集」
自註現代俳句シリーズ一一(二六)
- 三月十日
葺き替へて藁屋根青空より眩し 高橋悦男 「蘭」川崎支部の人たちと鎌倉へ吟行。谷戸を歩いていたら葺き替えたばかりの藁屋根の家が見えた。農家ではなく別荘風の家だった。
「高橋悦男集」
自註現代俳句シリーズ一一(三五)
- 三月十一日
湯豆腐や流氷の牙夜も見えて 澤田緑生 網走の旅荘から庭づたいに流氷の中に散策道が出来ていた。夜は部屋から峨々と打ち重なった流氷の牙がするどく眺められた。
「澤田緑生集」
自註現代俳句シリーズ五(一七)
- 三月十二日
水草生ふ放浪の画架組むところ 上田五千石
先生の書斎の棚に、俳句の本はもとよりひと際光彩を放っていたのは、旅の本と美術全集だった。旅の本には深田久弥の百名山、美術全集は印象派以降の画家の本が、書架の一等地に並んでいた。自註句集でいうように、旅への憧れが作らせた。(水内慶太)
「上田五千石集」 脚註名句シリーズ二(一五)
- 三月十三日
お松明走れば走る人おろか 宇咲冬男 二月堂のお水取りは、火と水の祭り。闇を照らしてお松明がお堂を走ると、人波もそれにつれて揺れ動く。〝おろか〟とは自分へも投げた言葉。
「宇咲冬男集」
自註現代俳句シリーズ五(六)
- 三月十四日
花いまだにて西行忌月夜なり 有働 亨 その年の陰暦二月十五日、西行忌の日はぽっかりと満月が東の空に浮んだ。陰暦と陽暦の差のせいか、西行の恋いこがれた桜はまだ蕾が固かった。
「有働 亨集」
自註現代俳句シリーズ四(一二)
- 三月十五日
涅槃図に頭だけ間に合ひしもの 杉 良介 涅槃変を知って、生きとし生けるものが駆けつけたが、涅槃図の端にやっと頭しか描いてもらえなかったものもある。
「杉 良介集」
自註現代俳句シリーズ九(七)
- 三月十六日
温みつゝ水いと浅く流れをり 星野立子 三月十六日、横浜西ロータリーへ講演に行った日である。午後は三渓園に小句会で集る。だんだんに大風となりつつあった日、水温んできて春らしくなってきたという句、今でも三渓園では月一度句会をしている。
「星野立子集」 脚註名句シリーズ一(一七)
- 三月十七日
職辞して馬鈴薯植うることなども 下里美恵子 三月、栗田先生が日大を辞職された。「これから少しは自分の時間が持てるよ」と楽しそうに話された。
「下里美恵子集」
自註現代俳句シリーズ一一(四九)
- 三月十八日
安達太良や彼岸の雪の二尺ほど 今井杏太郎 安達太良山は、また乳首山ともいうとある。その安達太良の北側に鴉の群棲地のあることをあとで知った。
「今井杏太郎集」
自註現代俳句シリーズ六(四六)
- 三月十九日
ひと組の板桶となり鳥雲に 中村雅樹 東海道五十三次の四十七番目の関宿。ここで「関の山」という言葉が生まれた。桶を作っている店があり、その様子を興味深く眺めたものである。
「中村雅樹集」
自註現代俳句シリーズ一三(二〇)
- 三月二十日春分
風に歩む前歯つめたし卒業期 坂本宮尾 卒業は何かの業に終止符を打つことであるが、それはまた新世界への船出でもある。三月は別れと新たな出会いへの感慨と緊張に満ちている。
坂本宮尾 『別の朝』平成十八年
- 三月二十一日
唄ふごと魚糶る声や燕来る 伊藤秀雄 何処の漁港でも糶場は活気があり、句作の狙いどころである。呪文のようにも聞こえ、あれで糶が出来るのかと感心する。
「伊藤秀雄集」
自註現代俳句シリーズ一三(一)
- 三月二十二日
外梯子濡るる春雪降るかぎり 田村了咲 二階建てのアパート、何世帯か住んでいる。淡雪が降って、外梯子を濡らす。外梯子だから当然なことだが、春の雪に濡れるのは何か悲惨である。
「田村了咲集」
自註現代俳句シリーズ二(二二)
- 三月二十三日
落椿芯に小穴の抜けてをり 松永浮堂 三月、研修も終盤。教員仲間と箱根での研究会に参加した。宿の近くで落椿を見つめる。見つめることこそ俳句の基本。落椿は美しくも虚しい。
「松永浮堂集」
自註現代俳句シリーズ一二(六)
- 三月二十四日
謡ふ父見え朧夜の続きをり 小川かん紅 小学校三年生の時に失った父の記憶は、数えるほどしかない。見台の前に端座して独得の節まわしで唸っていた父の面影はよく覚えている。
「小川かん紅集」
自註現代俳句シリーズ八(四八)
- 三月二十五日
雑木の芽日に日に名乗りあげにけり 小浜史都女 葉を落していた樹木が春の訪れとともに芽吹いてきた。裸木ではわからなかった木の名前が芽吹きとともに私たちに教えてくれる。
「小浜史都女集」
自註現代俳句シリーズ一一(三四)
- 三月二十六日
木下ろしの痕ありありと春の山 染谷秀雄 紫陽花の葉が出始めた三室戸寺へ向かう。境内には蓮の甕が累々と並ぶ。木下ろしをした痕が長々と付いている宇治の春の山を近くに見た。
「染谷秀雄集」
自註現代俳句シリーズ一三(二八)
- 三月二十七日
職退いて疎遠椿の花蕾 木村里風子 同僚が退職したが一年位は時々顔を出していた。いつのまにか来なくなった。
「木村里風子集」
自註現代俳句シリーズ一一(一二)
- 三月二十八日
職退けば一国鉄の東風の駅 亀井糸游 これまでは職場のつづき、わが社の駅と見ていたが、今日からはそうはいかぬ。三十余年間の国鉄生活を離れた覚悟と感懐。
「亀井糸游集」
自註現代俳句シリーズ二(一三)
- 三月二十九日
外厠戸がぎいと鳴り春の山 山上樹実雄 宇陀から室生へ赤埴の集落を過ぎてすぐの山間に仏隆寺がある。かつての隠れ里も今は古木の大桜へ物見の車が集まる。急に厠の戸が、春の風だ。
「山上樹実雄集」
自註現代俳句シリーズ五(五五)
- 三月三十日
春茸を干し足音の澄める村 神尾季羊 椎葉の鶴富屋敷。平家の血すじだという老婆が、伝承の書簡や巻物などを見せてくれた。真昼しずかな庭に一筵の春茸が干してあった。
「神尾季羊集」
自註現代俳句シリーズ四(一七)
- 三月三十一日
税金が返つてくるよ桃の花 草間時彦 納税期、確定申告は、新季語として少しずつ認められつつある。確定申告のあと、しばらくして税金の還付通知が来ることもある。もとは自分のお金とはいえ、納めた税金が戻って来るのは一種格別な気持である。〈税申告気になつてゐる寝酒かな〉。(山崎ひさを)
「草間時彦集」 脚註名句シリーズ二(一)