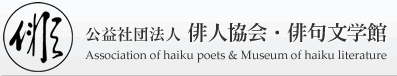今日の一句
- 七月一日
快晴の快風の山開きけり 三田きえ子 「畦」の恒例となっている富士の山開き、快晴の快風のリズムが楽しい。
「三田きえ子集」
自註現代俳句シリーズ七(一四)
- 六月三十日
草を手に子の遊びをり御祓川 中村雅樹 京都で「晨」の同人総会が催された。上賀茂神社の楢の小川で遊んでいる子どもを詠んだ。山本洋子さんと中山世一さんの選に入ったと記憶。
「中村雅樹集」
自註現代俳句シリーズ一三(二〇)
- 六月二十九日
青山椒雨には少し酒ほしき 星野麦丘人 六月、伊香保温泉で鶴俳句鍛錬会がひらかれた。天候には恵まれなかったが、友二賞を獲得した。「降りぐせの山の宿なり炙花」は同時作。
「星野麦丘人」
自註現代俳句シリーズ二(三四)
- 六月二十八日
手を振りて母が来さうな青田道 髙田正子 そろそろ植田から青田になる頃合いかと考えていたら、不意に亡き母が現れた。いつもこうして出迎え、帰るときには見えなくなるまで見送ってくれた母である。
髙田正子 2021年作
- 六月二十七日
蛭つきて水物花材届きゐし 朝倉和江 いけ花の材料には虫がついていることがある。大嫌いな毛虫も殺さねばいけ花教師はつとまらない。河骨には蛭がついてくることがあった。
「朝倉和江集」
自註現代俳句シリーズ五(二)
- 六月二十六日
金串のベーコン熱き青葉木菟 松本澄江 浅間大滝を見に奥軽井沢のロッジによく立寄った。空気が冷たく金串で焼いたベーコンがうまかった。青葉木菟がホーホーとよく鳴く。
「松本澄江集」
自註現代俳句シリーズ六(二九)
- 六月二十五日
樹上にも緑蔭ありて鳩憩ふ 八木沢高原 緑蔭に休んであたりに注意を払うと、頭上に鳩がとまっていた。樹上に緑蔭があっても不思議はなく、鳩の緑蔭は樹上なのかと思った。
「八木沢高原集」
自註現代俳句シリーズ四(五二)
- 六月二十四日
蛇消えしあと草むらに風立ちぬ 柏原眠雨 宮城県の白石から七ヶ宿方面へ入った小原温泉に結社の吟行で出掛けた折の句。白石川上流の碧玉渓と呼ばれる谷を歩いて、蛇に出くわした。
「柏原眠雨集」
自註現代俳句シリーズ一一(六六)
- 六月二十三日
八つ目鰻割く吸盤に指入れて 吉田紫乃 田の水口に居たからと八つ目鰻を貰う。魚屋へ頼んで手捌きを見る。
「吉田紫乃集」
自註現代俳句シリーズ七(三〇)
- 六月二十二日
砂糖壺に砂糖充実水中花 澤村昭代 砂糖壺にもたまにはいっぱいの時もある。水中花とのとり合せが面白いといわれた句。
「澤村昭代集」
自註現代俳句シリーズ八(三七)
- 六月二十一日夏至
菩提樹よ沙羅よ仏の夏木とす 加藤三七子 菩提樹は鶴林寺に、沙羅は応聖寺に、どちらもいい木で私の好きな木である。花の咲くとき実のつくときかならずたずねたくなる木。
「加藤三七子集」
自註現代俳句シリーズ三(一〇)
- 六月二十日
薫風に乾けり真間の泪石 河府雪於 真間吟行。手古奈堂から弘法寺に通じる石段があり、その一つ少し幅広の石を泪石と呼ぶ。万葉の手古奈の泪とでもいうのであろうか。
「河府雪於集」
自註現代俳句シリーズ六(一八)
- 六月十九日
江戸城址雀こもらす夏柳 村田 脩 ここは、堅固な構えを抜け、お濠を渡ったあたりか。
「村田 脩集」
自註現代俳句シリーズ三(三五)
- 六月十八日
一つ名の川が海まで青嵐 伊藤白潮 前句と同じく木曾川そのものを詠んだ。翌朝のタクシーで赤沢美林へゆく途中、運転手に確めてみた。「この川は海に入るまで木曾川ですか」。
「伊藤白潮集」
自註現代俳句シリーズ五(六一)
- 六月十七日
鮎宿に持ちこまれたる地酒かな 皆川盤水 浦佐の魚野川に鮎漁をした時の句。沢木先生に同行した。酒を持ちこんだのは私。
「皆川盤水集」
自註現代俳句シリーズ三(三二)
- 六月十六日
紅花を植ゑて教師の余生あり 細谷鳩舎 紅花は雪解と共に植え、半夏の頃より咲き始める。教師をしながら、紅花研究を始め、晩年はその権威となった。
「細谷鳩舎集」
自註現代俳句シリーズ五(三四)
- 六月十五日
奔流の荒き水の香額の花 大岳水一路 雨のあと、水嵩の増した奔流の匂いは荒々しい。郊外にある慈眼寺の渓谷である。額の花もまた雨の後が美しい。
「大岳水一路集」
自註現代俳句シリーズ六(四四)
- 六月十四日
硝子戸に子が顔つけて梅雨深し 小倉英男 梅雨がつづき日曜日になっても晴れない。遊びに出られない息子はうらめしそう。硝子戸につけたその顔がいびつに見えた。
「小倉英男集」
自註現代俳句シリーズ八(三四)
- 六月十三日
足のばしゐてもひとりや梅雨畳 舘岡沙緻 箱根・若葉年次大会での作。風生先生の特々選となり同室のあやさん、眸さんによろこんでいただきホッとする。
「舘岡沙緻集」
自註現代俳句シリーズ七(一二)
- 六月十二日
仰ぐかぎり梅雨の青嶺や小海線 古賀まり子 小海線は乗っているだけで楽しい。勿論、一人旅。
「古賀まり子集」
自註現代俳句シリーズ四(二二)
- 六月十一日
夜間授業待機のながさ梅雨西日 石田小坡 全日制の授業のあと、定時制の授業が始まるまで二時間半、テニスやバレーボールなどで汗を流した。俳句には不熱心だった。
「石田小坡集」
自註現代俳句シリーズ六(五二)
- 六月十日
郵便配るこの身が時計の時の日よ 磯貝碧蹄館 「あの郵便屋さんが来たから何時だ」と時計がわりにしてくれる。働くことの幸福を、こうしたことに味わえるのは嬉しいものだ。わが最良の日。
「磯貝碧蹄館集」
自註現代俳句シリーズ三(二)
- 六月九日
うつし世のものと灯りし蛍かな 清崎敏郎 蛍火が現実世界のものとして灯ったということだが、現実に目の前にある蛍をわざわざ「うつし世のものと」ということによって、蛍火にこの世のものではないような幻想性が加わる。しかもあくまでも現世のものであるくっきりとした美しさもあるのだ。(大輪靖宏)
「清崎敏郎集」脚註名句シリーズ二(二)
- 六月八日
螢とぶ闇に起伏のある如し 今瀬剛一 我が家と山一つをへだてた田んぼではいまでも螢が乱舞する。「闇に起伏のある」は私の実感から生まれた表現である。
「今瀬剛一集」
自註現代俳句シリーズ六(三三)
- 六月七日
興聖寺の門前を飛ぶ螢狩る 石井桐陰 家内と二人、夕方に家を出て、宇治川の螢を見に行く。興聖寺の琴坂にかかる門前に、大きな螢が飛び交うているのをつかまえた。
「石井桐陰集」
自註現代俳句シリーズ四(六)
- 六月六日
細む眼に百言余し著莪の花 多田薙石 清瀬東京病院にて。先生はまた入院された。もともと細眼の先生だが、にこにこされると一層細くなる。
「多田薙石集」
自註現代俳句シリーズ六(一五)
- 六月五日芒種
てぬぐひの如く大きく花菖蒲 岸本尚毅 句帳にははじめ「白菖蒲」と書いた。最終的に「白」を消したのは「広々と紙の如しや白菖蒲 星野立子」という句を意識したから。
岸本尚毅 句集『鶏頭』所収
- 六月四日
螢袋登四郎の訃を旅にして 吉田鴻司 大阪淀川支部の吟行で兵庫県の龍野を訪れている。能村登四郎は、「沖」の創刊主宰。「沖」と「河」は古くは若手吟行会を開いたり浅からぬ縁であった。登四郎の〈蛍袋に指入れて人悼みけり〉を踏まえた、旅先での悼句である。「吉田鴻司集」
脚註名句シリーズ二(一六)
- 六月三日
朴咲けり湯殿おろしの荒息吹 高島筍雄 湯殿山登拝。朴が咲き、水芭蕉が群れ咲いていた。六月とは言え、手足はこごえるばかりだった。
「高島筍雄集」
自註現代俳句シリーズ六(三〇)
- 六月二日
- まだ生きて蜘蛛に抱き締められてをり
望月 周 自販機横の蜘蛛の巣。蜘蛛が巣を去っても、灯りに誘われて羽虫がかかり続けます。干涸らびる死を見詰めながら、蜘蛛に抱かれる死を思います。
望月 周
作句年:令和3年(2021年)